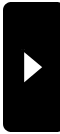2024年12月30日
12月23日は2024年の研修日の大トリでした。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、ウェブ担当の宗風です。
落語、演芸から出た言葉で、
いちばん最後の出番を「トリ、トリを取る」なんて言いますね。
お耳に達しておられる方も少なくないのではないでしょうか。
それをもっと強めた言い方が「大トリ(おおとり)」ですね。
例えばこの時期の紅白歌合戦ならば、
先んじてどちらかの組の最後の出番をトリ、
紅白歌合戦全体の、次の出番、最後の最後を大トリなんと申します。
12月23日の欅の森書道会、この研修日はつまり、
2024年の大トリでした。
今年1年、皆々様お疲れさまでした。
また熱く指導して下さった樋口玄山先生、
本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。
そんないよいよの年末、
本日もブログの幕が開くと言うことになってございます。
どうぞ終いまでお付き合いのほどを願っておきますが…。
・
・
さて。
年明けは1月6日からですね。
競書の提出日となります。
今回の【基本】課題「皓々白於雪」は前回のブログにて解説しております。
( https://keyakinomori.naganoblog.jp/e2810993.html )
南洲、西郷隆盛の漢詩の一節になります。
【隷書条幅】課題「佛日増輝」の解説はこちら。
( https://keyakinomori.naganoblog.jp/e2809894.html )
仕上げて行く際に参考にしていただければと存じます。
ご連絡としてはこちらも。
23日に御子柴さんと共に大切な作品をお預かりいたしました。
松本市美術館にて,2025年1月5日から16日までの会期で、
「第23回美術館友の会 会員作品展」が開催されます。
美術館が6日,14日と休館となりますので、
併せてお休みとなりますが。4日に飾り付けをして参ります。
どうかご都合つけば、お出掛けください。
・
・
いくつか徒然なる話題などを…。
今年の漢字、「金」…4度目?5度目?何度目かの選定でしたね。
ご覧になった方も多かったのではないでしょうか。
草書的な「金」だそうです。一見だと「全」や「垂」に見えるかたち。
書法辞典で見てみても、
2画目にもうひとつあった方が…などと自分は思ってしまったのですが、
ウェブ上の識者の皆様だと「アリ」なのだそうです。
書道的な観点からご覧になっても、少し参考になるかも?どうでしょう。
・
塩尻市の市民憲章の件、少しだけ進展がありました。
塩尻市ロータリークラブの職員さんが調べて下さった内容、
このご連絡を頂戴しました。
本当にありがとうございました。
古い資料となり、ご苦労されたのではないかと思います。
心より感謝申し上げます。
して、結果は。
塩尻市ロータリークラブに残っている記録だと、
当時、「塩尻市に寄付をした」と言う記録があるそうです。
しかし、同時に石材屋に?書道家?デザイン会社?…
そうした寄付以外の記録が残っていないとのこと。
この記録はロータリークラブ発足と同時なので、
あるならば、ちゃんと残っているべき内容だと言うのです。
しかし、無い。
紛失を考えないならば…ここからは想像とのことですが、
寄付した塩尻市におまかせしたのではないか?
…と思われる。なるほど、それはあり得ますね。
塩尻ロータリークラブの歌…であれば、
ロータリークラブに記録がありそうなものですが、
何と言っても塩尻総合文化センター前、市の関連する土地の上に、
塩尻市の市民憲章の石碑を立てる、となれば、
寄付を受け取った市がそのお金を使って、
市民に役立つものを建てた…と言う流れ、違和感がないですね。
前回、市役所に問い合わせを行った際は、
文化関連の職員さんが当時の新聞などを調べたそうです。
もう一歩、踏み込んでもらえるならば、
情報の糸口、掴めるでしょうか…。
こちら年明けにでも対応してみたいと思います。
繋がって行くと良いのですが。
…と、実はここまで書いていたのは24日前後。その後の慌ただしさで、今になってしまいました。もう30日です。あっという間に年の瀬ですね。どうぞ皆様、良いお年をお迎えくださいませ。
本日はこんなところでお開きとさせていただきたく存じあげます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年12月10日
12月9日は欅の森書道会12月1回目の研修日でした+「仏日増輝」について。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、ウェブ担当の…
お馴染み様でございます。宗風です。
いやぁ、お寒ぅございますねぇ。
昨晩も元気に会社からの半袖にてお邪魔致しました。
暖房をね、しっかりと焚いて下さるので、案外寒くはないのです。
ただ外に出たりすると寒いですし、
あとは肌が外気に触れていなければ…と最近感じますね。
急に冬になったようにも思います。
天気予報からは12月末から1月末の気温である、と。
信州スカイパークをお休みの昼に走ったりなんぞ致しますが、
それが氷点下…と言う期間は、実は案外少ないんですよね。
厳冬期のみ。
日中はお日様の温かさがあって、
温度計以上に感じたりもする事もありますね。
さて。
昨晩は競書で申しますと2024年12月号の2回目の添削でしたね。
〆切でした。皆様ご提出されましたでしょうか。
今月も課題への取り組み、励み、お疲れさまでした。
・
・
来年以降の教室の研修日、予定が定まりました。
以下の通りです。

2024年(令和6年)
12月23日:2024年最後の研修日
2025年(令和7年)
1月6日:競書〆切(2025年1月号)
1月20日:
2月10日:競書〆切(2025年2月号)
2月24日
3月10日:競書〆切(2025年3月号)
3月24日:書象展〆切
4月7日:競書〆切(2025年4月号)
4月21日
以上、現段階発表の予定でした。
・
・
トピックスとしましては、
信州書象展、盛会御礼を申し上げます。
足をお運び下さった方、皆々様、誠にありがとうございました。
欅の森書道展とはまた雰囲気が違った展示となりましたね。
毎回思う事ではありますが、それぞれに思いがある訳でして。
同じ書象会の仲間であっても、
書風の違いに触れると勉強になることも多ございますね。
欅の森書道会としましては、
次のイベントとしては「書象展」になると思います。
県展の巡回が松本市美術館にやって参りますので、
週末、2024年12月13日(金) 〜 2024年12月15日(日)が会期となっております。
また欅の森書道会の会員も多く参加しております、
松本市美術館友の会が主催する
「第23回美術館友の会 会員作品展」が、
2025年1月5日(日) 〜 2025年1月16日(木)で開催されます。
(6日、14日が休館日です)
この件につきましては、
次回の欅の森書道会の研修日、12月23日に、
作品をお持ちになって頂ければ、
私や御子柴さんで搬入展示を行いますので、
是非、作品を出品して頂けますと幸いです。
むしろ、未加入の方もこの機会に友の会の会員になって頂けると、
すごーく有難いです。
…と、ご連絡事は以上です。
・
・
さて、次回2025年1月号の競書から、
【隷書条幅】の課題、樋口玄山先生よりお預かり致しました。
「佛日増輝」
仏の日は増して輝く。
「佛」は「仏」の旧字ですね。
「輝」の形が「光に軍」ではなく、「火に軍」となっております。
以前に教えて頂いた「書法辞典」で検索を掛けてみると、
なるほど碑文の「輝」の例に「火に軍」の形も多くありますね。
調べてみますとお寺さんの記事に多く当たります。
「奉造立本堂 佛日増輝 法輪常転」
これは千葉県の浄土宗浄蓮寺さんのウェブサイトから。
お札に書かれている言葉だそうです。
本堂立ち造り奉る、仏日は輝きを増し、法輪は常に転ず」と言う。
静岡市清水区の東光寺さんんお大般若祈祷会のお札には、
「天下泰平、五穀豊穣、佛日増輝、諸縁吉利」とあります。
人の願いの中にあり、
仏様のご威光がずーっと広がって行きますように…と言うのは、
お経の中にどの仏教にも通じて存在する感覚だと思います。
石川県加賀市の「実性院」の入口には石碑があり「皇風永庵・佛日増輝」とあるのだそうです。
神社で言う「縁起」…とはまた少し、神道とは違うのかも知れませんが、
願い、掲げたいお題目…そんな風にも感じますね。
仏様の日について何を思うか…と言えば、平和、泰平、穏やかな印象でおります。
新年に向けて、そうありたいと選ばれた課題なのではないでしょうか。
そうです。小島紫草さんの添削の際に「書初めに書こうと思って…」と1枚、
お持ちになって先生に見てもらっておりました。
寒さだけでなく、そうしたところもついに師走、年末なのですね。
次回、欅の森書道会は12月23日です。
厳しい寒さ、激しい乾燥の季節になっております。
どうぞご自愛しつつ、励んで参りましょう。
それでは、本日はここまで。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年11月26日
11月25日は欅の森書道会の研修日でした。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市、欅の森書道会のウェブ担当の宗風です。
お馴染み様でございます。
さて、前回の色んな〆切が重なった頂の様な研修日を経て、
11月25日、11月2回目の書道教室は、
少し落ち着いたのかしら…なんて思うところでございました。
信州書象展が週末の11月29日、30日、12月1日とございますね。
その直前準備と言う所も見えながら、
この2024年、欅の森書道会の研修日も、
残すところは12月の2回となりました。
12月9日と12月23日となっております。
年の瀬に近付いて来ましたね~。あっと言う間ですね。
ご連絡事項と致しましては、
25日も御子柴さんより連絡があったかと思いますが、
松本市美術館友の会、友の会展が1月にありまして、
こちらの出品を募っておりました。
会員特典の多い「友の会」にご入会頂き、
出品をして頂けますと幸いです。
不明点、また作品の預かりに関しましては、
御子柴さんや私にお声掛け頂ければ対応できますので、
どうぞ、よろしくお願い致します。
年を明けますと…その前からも…
そろそろ書象展へのお手本を、
どんな字、詩などお考えになっても良い季節となっておりますね。
欅の森書道展の講評の中で、
樋口玄山先生より、
「先生、こう言う詩を書きたいのですが…」と、
課題についてリクエストが出ることが増えた、との事でした。
素敵ですね。
自分自身で探し、良いと思った詩や句を作品として仕上げる。
これは書道を楽しむ者の特権ですよね。
そして、気に入った言葉をまず玄山先生にお手本で書いてもらえる…
これもとても特別な事だと感じています。
次なる「信州書象展」について自分は、
「轟勢元気溌溂」と言う言葉をお願いしました。
これ中国や日本の詩歌の一節ではありません。
日本酒のラベルに書かれている「雅詞(みやびことば)」と呼ばれるもので、
現代的なラベルにはもう存在しないものです。
むしろ祭事の「菰樽」に残っていたりしますね。
古いスタイルのラベルにあります。
例えば信州諏訪・真澄なら「名聲布四海」とか。
銘柄の左横に赤字でちょこんと。
他にも「名聲秀天涯」だったり「名誉秀天涯」など、
少し変えたものもあればオリジナルの和歌だったりする場合もあります。
「元気溌溂」は信州中野市の「勢正宗」の雅詞。
これに他で見掛けた「轟勢」を足して作ったものだったりします。
すっごい強い勢いで「ゲンキハツラツ!」が良いなぁ、と。
先生の解釈、お手本は本当に素晴らしく、
近付けるように頑張りましたが…さて、それは会場で…
…と言えると良いな。頑張りましたので見て頂けたらと思います。
何はともあれ。
書象展の場合は課題に向く、相応しい詩文もある形ですので、
その辺りから選ぶなどして先生にお願いしたい所ですよね。
こちらも励んで参りましょう。
本日はここまで。
ちょうどお時間となっております。
お付き合い頂きまして誠にありがとうございました。
それではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年11月14日
11月11日は欅の森書道会、11月1回目の研修日でした+「青山如故人」について。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、ウェブ担当の宗風です。
お馴染み様でございます。
先週は「もう冬か」と思う程寒いなぁ、と言う日々でしたが、
今週に入ってまた少し戻って来ましたかねぇ。
教室にも新しいピカペカのストーブが入荷しておりましたが、
さて、11日の夜から明けて、いかがお過ごしでしょうか。
写真は全く関係ないのですけれど、
宗風家に新しくお迎えした文鳥のピーちゃんです。
…添削前後、早く会いたくてウキウキしていたので、
教室の様子、そんな写真を撮り忘れたのです。
ブログ、写真がないと「NO PHOTO」的な紹介になってしまうので、
それを避けたく、可愛い身内をウェブの波に流そうと言う…
…職権乱用の様にもちょっと感じたりもしながら…。
11月4日におおよそ生後1か月と言う、
雛ではないけれど幼子の文鳥です。可愛くて仕方がありません。
ちゃんと育つかな、と常に心配をし、
心配するあまり、ピーちゃんの食事量はバッチリなのですが、
私の食事量が減り、お酒をほぼ飲まなくなり、
早寝を心掛ける様になり、
朝のピーちゃんのご飯の為に早起きをする様になりました。
なんと健康的な生活に。
まだ慣れていなくてドキドキが…
部屋の温度は良いか、湿度は大丈夫か、育っているか、
色んな心配があって目が回る感じすらするのですが、ともあれ。
・
欅の森書道展を経て、欅の森書道会にも新たな…再び、ともなるのか、
新しい会員さんもご入会となったご様子。
何よりです。どうぞよろしくお願い致します。
ご挨拶をするべきだったのですが、そう、そわそわしており、
かつ、色んな〆切の11日だったので、
私宗風、インタビューなども含めて、ご挨拶をするタイミングが掴めませんでした。
いやはや申し訳ない事です。
次回以降に是非とも。
・
そんな次回が11月25日、
次々回、12月9日が競書の提出日で、
年内最後に12月23日が研修日として予定されております。
連絡としましては、
11月15日頃に競書誌「書象」の2024年12月号が届くはず。
11月29日から12月1日までの3日間、
信州書象展が松本市美術館、市民ギャラリーにて開催されます。
私達、欅の森書道会のみならず、
信州に住まう書象会の皆さんの作品が展示されますので、
また欅の森書道展とは雰囲気の異なる、
しかし上條信山門の書展となりますので、
是非とも足をお運び頂きたいと存じます。ええ、是非ともです。
併せて、松本市美術館コレクション展示も、
上條信山先生、また宮島詠士先生の書が展示中です。
こちら10月23日から入れ替わっておりますので、
以降、お出掛けになっておられない様でしたらオススメ致します。
ご連絡事項は以上です。
・
・
さて毎度お馴染み、課題になっている言葉、
その出典や意味、詩の全文などをご紹介致します。
課題に取り組むご参考になれば幸いです。
競書誌「書象」2024年12月号の【臨書条幅】は「行書」の課題。
「青山如故人」とあります。
「青山は故人の如し」、この場合の「故人」は現代の「亡くなった方」ではなく、
「旧友」と言う意味の様です。
その変換が正しく行われなかった私は、
「人間到る処青山あり」を想像した訳ですが、そうではないのでして。
(そして青山も、この言葉とは異なる意味ですね。もちろん東京の港区あたりでもありません)
この詩は明末清初の頃の「文點」の「渡江」と言う詩の一節です。
明王朝は1644年に清になっていますので、その時代。
文點は旧字交じり、「點」とは「点」の旧字に当たります。
原文としては以下の通り。
青山如故人
江水似美酒
今日重相逢
把酒対良友
以上となります。
一句目が今回の課題になっている、と言うことですね。
書き下し文だと以下の通り。
青山は故人の如く
江水は美酒に似たり
今日重ねて相逢い
酒を把って良友に対す
…となります。
「把って」は「とって」と読みます。
手にする、持つと言う意味ですね。
この場合の「青山」は素直に「緑生い茂る山」で良いと思います。
その景色を友人の様に思う、と。
「江水」は長江を示します。風景の中の長江は美酒の様だ、と。
日を重ねて今日もお互いに逢い、
酒を酌み交わすのは良友に対するそれの様だ、だから、
長江は友の様である…と言う、そんな意味の詩文と読みました。
ご案内の通り、欅の森書道会はお酒が好きな方が多く、
お酒にまつわる詩文が多いものですから、
こちらもどこかご縁を感じてしまいますよね。
明から清に移る激動の中を生きたからこそ、
穏やかな時間が表現されている様に感じられます。
・
・
…と、本日はこんなところで。
さて次回は25日ですね。
自分も信州書象展用に英語の案内、作らなくては。
きっと会場で使うと思いますし。
さてさて忙しい師走に向かっての11月も半ば。
励んで行きましょう。
本日もお付き合い頂きましてありがとうございまいた。
ありがとうございました。
2024年10月23日
10月22日は、10月2回目の研修日でした+若山牧水と喜志子。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当のお馴染み宗風でございます。
いやはや、グッと冷え込んで明くる日の月曜日、
そんな22日でしたね。
「お寒うございます」と言う挨拶をする季節になりました。
昨今、急に夏や冬が来る、秋や春がなくなって、
四季が二季になったんじゃないか…と言うお噂を聞く時代になって参りましたね。
テレビなんぞを見ておりますと、
流石に体が追い付いて来ないってンで、「秋バテ」と言うそうですよ。
「秋バテ」
夏バテに続いて秋バテで、はてその前の初夏あたりなんかは、
「五月病」もありますよねぇ。
冬はインフルエンザなどなど猛威を振るったりもするならば、
安住の生活は何処に…と言う事ですが、
本日も気楽なところで一生懸命…と言うことです。
しばらくの間、お付き合いを願っておきますが…。
・
さて、次回の欅の森書道会の研修日は11月に入りまして、
11月11日となっております。その次が、25日に設定されておりますね。
11月11日は既報の通りでして、様々な〆切となってございます。
よって、昨晩はそれを前に熱心に皆様お集まりになった…が、
やはり体調の優れない方もいらっしゃった様子、と言う所の様です。
トップの写真は樋口玄山先生の添削、ご指導を、
熱心に拝見する教室の皆々様。
外は寒くなっておりますが、ね、気持ちは熱いままでございますね。
昨晩はストーブもついに稼働しておりまして、
上のヤカンもチンチンになっておりましたけれども。
さて、ご連絡。
11月11日は、月初ですので月例でお月謝を集めます。
昇段試験の締切り日ですので、昇段試験料を集める事になるはずです。
また信州書象展への作品締切り日でもありますから、
大谷表具店さんがお見えになり、
こちらも大谷さんへ発注される場合は注文をすることになりますね。
何かと物入りで、用意をせねば…と言う所でございます。
冬支度の前に作品制作ももうひと踏ん張りですね。
励んで行きましょう。
・
・
さて、今回の課題の解説なのですが、
【仮名】に若山牧水が取り上げられておりましたので、
少し牧水について、ご案内のことも多いとは存じますが、
語ってみよう、なんてご趣向でございます。
信州にゆかりのある若山牧水。
酒仙、酒豪として知られ、佐久市望月にあります武重本家酒造には、
「牧水」と言う酒銘の日本酒があったり致します。
ゆかりがあるので、こんな歌も歌碑となって蔵に残っている様で。
「よき酒と ひとのいふなる 御園竹 われもけふ飲みつ よしと思へり」
「良い酒と聞く御園竹(みそのたけ)、自分も今日飲んでみて良いと思ったよ」
…と、実にシンプル。こんな風に言ってもらえたら蔵元さん、嬉しいでしょうねぇ。
今回、競書誌「書象」の11月号の【仮名】、段位師範向けの課題として、
牧水の以下の歌が取り上げられております。
「ひそまりて 久しく見れば遠山の 日なたの冬木 風さわぐらし」
これをWeb上で検索してみると、
静岡県伊豆市土肥の地に、この歌の碑があるそうです。
牧水が好んだ海に近い松原公園に、昭和45年8月に建てられたのだとか。
若山牧水は、本名を若山繁(しげる)と言い、
明治18年、1885年に生まれ、1928年に没しております。
享年は43歳ですので、随分と若い。
お酒好きとして知られ、やはりお酒が元で無くなった部分もありそうです。
それは敬愛する古今亭志ん朝や十代目金原亭馬生にも通じる所があり、
何とも思う所がない訳ではないのですが…ともかく。
現日向市、宮崎県の東臼杵郡坪谷村に生まれます。
中学校時代から短歌、俳句を始めており、18歳に母「まき」から1字、水は生まれ育つこの地、周囲にあるものから取って…と、自ら「牧水」の号を定めたそうです。
1904年に早稲田大学に入学。1908年に卒業。7月には初の歌集「海の声」を出版。
1911年に「創作社」を起こし詩歌雑誌「創作」の主宰となる。
この年に当時の広丘村出身の太田水穂を介して、水穂の親族である歌人、太田喜志子と出会う。
太田喜志子は吉田村ですから、今の広丘吉田の辺りですよね。
ここで塩尻市と牧水の縁が出来る…と言う訳でして。
夏に塩尻市短歌館に出掛けた際に、
太田水穂や太田喜志子、青丘や島木赤彦の歌、また色紙などを見て来ました。
その時はぼんやり「何か関連があるんだろう」くらいに受け止めていましたが、
島木赤彦の詩も「書象」では採用されていましたし、
やはり郷里の偉人への敬意がある様に思います。
牧水はその後、1920年に沼津市に移住しています。
これは千本松原の景観を大いに気に入ったから…とのこと。
静岡県が計画した千本松原伐採工事にも異を唱えて断念させたそうです。
1927年、1928年と体調を崩し牧水は亡くなる訳ですが、
詠んだ7000首近くある歌や詩の中に、お酒がテーマのものは200首ほどあるそうです。
「牧水全集」(全12巻)は牧水の死後、喜志子がまとめたもの、とのこと。
今後も信州、郷里に関わる偉人として、
牧水の詩や歌などを課題として書くこともあると思います。
そんな若山牧水について簡単に語りまして…
…と言った所で、本日はここまで。
お開きの時間となっております。
ではまた。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年10月19日
「山光照我心」と「明月不留人」と教室の予定と昇段試験など。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当の宗風です。
本日もしばらくの間、お付き合いを願っておきます。
さぁて、週明けに書道教室の日が近づいて参りまして。
課題のひとつの締め切りになる訳ですから、
こう、少し焦りつつある…なんて所でございます。
次回、欅の森書道会の研修日は10月21日ですね。
次々回は11月11日…これが色々の〆切り日となります。
このお知らせをせねば、気が気でなくて夜しか眠れません。
10月21日としてのご連絡は、
信州書象展の申込、出品料などについて気にする、
お持ちになっていない方にはご連絡…と言った所かと。
次の11月11日に、大きな区切りがございます。
・競書11月号分の課題提出日
・昇段試験の作品提出日、競書10月号分と11月号分について。
・信州書象展、大谷表具店さんへの表装分、提出日。
以上です。
重なり重なる、なかなかたいへんな状況ではありますが。
あとは月始めになりますので、お月謝の集金も。
銘々様、どうぞお支度のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
…と、ご連絡はここまで。
続きまして、
言葉の解説なぞ入れ込もうと考えてございますが…。
解説のひとつめ。
条幅の課題には、「山光照我心」とあります。
出典が見当たりませんでした。
「山光は我が心を照らす」…と書き下し文の形を取ります。
うむ。そのまま読んでも意味がだいたいは分かる並びですね。
検索してみると1字変わって「山光澄我心」が多くヒットします。
高野山に関りがある様子。
また書道のお手本として使われている様子が伺えます。
「山光に我が心は澄む」と言う。
これは山の光?とは、山の中での光?山が光っている?
諸説意味はどれも通ると思うのですが、
どうでしょう、朝日などの山から差す強い光を言っている様に感じます。
「山光照我心」、心が照らされるような朝日。山からの。
何と胸がすく光景なのでしょう。
「山光澄我心」では照らされ、
心のわだかまりが解ける様なニュアンスになる気が致しますねぇ。
心の在り様は仏教の根幹ですから、なるほど…と言う心持ちです。
・
さて、続きまして「基本」の課題。
「明月不留人」
これは「明月、人を留めず」、良い月は人を留めない…と言う意味か。
こちらも出典を見つける事が出来ませんでした。
なので、正確に言葉の意味が分からないので、想像で書いて行きます。
ご参考程度として頂きたく…。
「明月、人を留めず」、イメージの上ですと、
スーパームーンだ、ブルームーンだ、色んな呼び名があって、
最近は天気予報で言ってくれまして、「まぁキレイ」なんて感じで、
月を見る機会が増え、その時の自分を思い出しますと、
足を止めている様な心持ちです。そうですよね?
良いものがあれば足を止める。そう言う風情。
…すると、この言葉の意味が合わなくなってしまっていますね?
では、と考えてみますと、
これ、現代の様に明るくない時代のことですから、
旅人としては、移動できるのは昼日中だけですね。
夜は…では、懐中電灯で行きますか?そんなものはない?
なら、たいまつ?ろうそく?提灯?
暗い山中は野盗が出たりもするでしょうし、
夜になったら宿に入って…と言う、それが常識の時代とすれば、
明るい月の中ならば、先を急ぐ旅人も足を止めない、阻まない。
かえって、それだけ明るい月夜の夜に。
その表現に感じます。
そう思って見てみると風流な響きになりませんか?
…と言ったところで、本日はここまで。
お付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年08月20日
8月19日は8月2回目の研修日でした+「雲来鳥不知」について。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当の宗風です。
お馴染み様でございます。
本日もお暑い中でございますが、
しばらくの間、お付き合いを願っておきます……と、
しかしてどうでしょうか、
朝晩は少しだけ暑さに翳りが見え始めましたでしょうか。
夏至の頃に比べれば、夜が早く訪れる様にもなりましたし、
何となく、どことなく、
まだまだ熱中症への警報だってテレビラジオで言ったりもしますけれど、
秋はそんなには遠い世界じゃないのかしら…
…なんて思ったりも致しますね。
昨晩に欅の森書道会の研修があり、
次いでは9月9日、9月23日でありまして、
更に10月4日、5日、6日で「欅の森書道展」がございます。
季節は涼しくなって参りますけれども、
意気は熱く過ごすことになりそうな、そんな時候かと存じます。
・
・
欅の森書道会の連絡網で、普段は15日に届けられる書象誌、
お盆期間もあって早めに届けられ取り組む事が出来ました。
連絡網があったから良いかしら…と、
前回のブログでは到着次第、記事を書くと言いながら、
本日まで漫然と致しておりまして。
ともあれ、そんなカタチで、
競書誌「書象」2024年9月号の課題へ入っておりますが。
9月号の条幅は「雲来鳥不知」の隷書5文字であります。
「雲来たれども鳥知らず」ですね。
調べてみますと、この言葉は本来は7文字ある詩の一部の様です。
「深樹雲来鳥不知」が原文です。
「雲が来たことを鳥が知らない」
…ことはあるのだろうか、ですね。空を飛ぶ鳥が雲を知らない=見れない状況とは。
先頭に「深樹」が入ると意味が少し変わりますね。
深い樹木、森の中にあって雲の流れを鳥が感じることが出来なかった…、
…と言う意味になるのではないでしょうか。
この言葉が含まれる詩は、
「山中酬楊補闕見過」と言う題の詩になり、
唐代の「錢起(せんき)」の作となります。
錢は銭の旧字ですね。
酬は報いる、返事をすると言う意味。
楊には柳、ヤナギの意味、
闕は宮城の門、またはその両脇にある物見やぐらを指す言葉だそうです。
山中の柳を補って報い、闕を見過ごす?
…山の中で柳を払いながら進んでいたら、宮城への入口を見過ごしてしまった…
そんな意味のタイトルになるのでしょうか。
全文は以下のような詩になります。
日暖風恬種藥時,
紅泉翠壁薜蘿垂。
幽溪鹿過苔還靜,
深樹雲來鳥不知。
青瑣同心多逸興,
春山載酒遠相隨。
卻慚身外牽纓冕,
未勝杯前倒接離。
薜蘿は、「へいら」と読み、つる草の様な植物を指します。もしくは隠者の衣服、住まい。
青瑣は、「せいさ」と読み、構造物の状態を指すカテゴリの言葉。
塀や装飾具、机…緑青(ろくしょう)を塗ったものを言うそうです。
卻は「却」の旧字。かえって、しかしながら。
纓は、「えい」と読み、冠の後ろに付く装飾具、または顎紐。
冕は、「ベン」と読み、「冠・かんむり」の意味を為します。
何となく意味、想像できますでしょうか。
方々調べてみたのですが、日本語の書き下し文が見つかりませんでした。
タイトルを踏まえつつ、特殊な上記の言葉をフォローすると、
何となく意味が見えて来る気がしませんか。
暖かく安らかな風が吹き、薬の為に種を撒く時期になった。
泉には赤(夕日)、壁には緑、つる草が垂れている。
奥深い渓谷には鹿が行き、苔むして静まり返っている。
森の深さは雲の行方を鳥に知らせないほどである。
青瑣と同じように心は落ち着かない。
春の山を思う楽しみな気持ちは、遠方より酒を飲みにやって来る時の気持ちに似ている。
しかしながら、後悔が後ろ髪を引く様に体を引っ張る。
勝利の盃を果たす前に倒れてしまった。
…と言う様に意味を解いてみましたが、はてさてどうでしょうか。
参考になる文献が無いと言うのは、実に心もとない。
しかし、漢字と言うものは1字1字に意味を持つので、
何となく、何となくは分かる感じがしますね。
…と、言う所で。
本日はここまで、お開きの時間と相成ってございます。
それではまた次回。
欅の森書道展への作品造り、頑張って行きましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年08月07日
8月6日は欅の森書道会、教室の研修日でした。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、お馴染みのWeb担当の宗風です。
本日もしばらくの間、お付き合いを願っておきます。
まずは8月6日、もうちょっと雨が降ってくれたら涼しかったろうに、
少しのお湿り、継がれた酒ならば少なさに暴動が起きよう…と言うものの様な、
そんなカタチでしたが…
そう、そうであっても炎天下の後の教室、と言うよりは、
少しは楽だったでしょうか。
蚊取り線香も焚かれており、夏の教室の風物詩と言えば、
歳時記と言えば、その通り。そんな8月1回目の教室でした。
県展の〆切がありますので、
松本市・大谷表具店さんにお越し頂きまして…
これから後述も致しますが、
欅の森書道会展が10月にありますので、
何度か大谷さん方には来て頂く事になる、と言った所でございますね。
Web上からも…ですが、よろしくお願い申し上げます。
先んじて、今後の予定などを書き記しておきます。
欅の森書道会、研修日としましては、
8月19日、9月9日、9月23日が予定されております。
9月9日、23日共に欅の森書道会展向けの作品〆切日の設定がございます。
出来るだけ9日に提出が理想とのこと。
なるほど、23日だと当日まで少し日がありませんね。
そして、10月4日、5日、6日で松本市美術館の市民ギャラリーにて、
「欅の森書道会・創設40周年記念書道展」が開催されます。
10月4日は13時から、6日は16時まで。
基本は9時から17時の松本市美術館の開館日に準じます。
以上、直近のご連絡でした。
・
先日の欅の森総会で個人的に「あ。」と思った事がありまして。
これまで「どう表現しようか」と思って、「開講日」とした書道教室の日、
会計の資料など拝見しますと「研修」となっておりますね。
講座開設の日なので「開講日」ですが、座して講じている様な、
議論の場と言う訳では無いので、適切ではないのかしら、と。
だので、総会の資料にあった「研修日」と言う表現に改めさせて頂きます。
・
次回、8月19日に見学の予定が1件、入っております。
17時頃にお見えになるそうで、宗風対応のこと、
池口さんにもご相談してあります。
書道を一緒に楽しむ仲間となると良いのですが。
さて、本日の所はここまで。
ちょうどお時間となっております。
お盆休み中は書象誌…毎年、どの様に届いておりましたでしょうか。
15日は平日なので、やはり15日でしょうか。
また入手しましたら、ブログに投稿しますね。
それでは。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年07月24日
7月22日は欅の森書道会、教室の開講日でした+正気の歌について

・
・
(いつもの土手の風景。山の稜線に日が落ちて行く、
稲が田んぼの中で育って来ており、視界に青が増えて来ましたね)
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、お馴染みWeb担当の宗風と申します。
本日は、いっぱいのお運び様でありがとうございます。
しばらくの間のお付き合いを願っておきますが…。
暑くなりましたねぇ、
そして蚊も元気いっぱいに飛び回る時期になって参りました。
蚊の来襲は本当に如何ともし難いですよね。
気が付くとやられている感じ。
ご苦労も多くなりつつ、7月22日も書道教室、開かれておりました。
次回は8月5日、競書の課題提出日となっております。
今回、樋口玄山先生に指導して頂いた内容を活用し、
再びお集まり頂けますよう、よろしくお願い致します。
・
今後の予定、教室の開講日以外の内容は、こちら。
第14回 欅の森書道展
→2024年10月4日(金) - 2024年10月6日(日)
第42回信州書象展
→2024年11月29日(金) - 2024年12月1日(日)
第65回松本市芸術文化祭参加 松本地区書道展
→2024年10月12日(土) - 2024年10月14日(月)
長野県書道展
→2024年12月13日(金) - 2024年12月15日(日)
また松本市美術館のコレクション展示、7月23日から第2期となっております。
上條信山記念展示室、今期は絵画の展示です。
以上です。
・
前回、全て書き上げられませんでした条幅の課題、
「凛冽万古心」について、続報…となるか分かりませんけれども、
書いて行きたいと存じます。
検索の上ですと、この言葉に行き当たらないのは変わらず。
「凛冽萬古在」、南宋時代の文天祥の「正気の歌(せいきのうた)」に由来があるとして、
この漢詩にまつわるお話をお伝えできれば、と存じます。
“忠臣の鑑”として現代に伝わる軍人、政治家とのこと。
彼の「正気の歌」は日本にも伝わり、幕末の志士に愛されました。
滅びゆく宋の臣下として戦い、
続く元からも才覚を認められ、勧誘を受けるのですが、
宋の臣下である、その心を変えることなく死を選ぶ…
捕虜と言う立場ですから、元の為に生きるか、次代を見ずに終わるか、
その中で死を選んだと言うのは、
尊王攘夷、死しても天皇制の復権の為に戦った志士に受け入れられた、と言う事ですね。
「凛烈として万古に存す」
「凛冽たる万古の心」
厳格さを尊いものとし、永遠に続く、象徴的である。
その厳格さは「正気」、信念そのものである。
想いを、強くすれば永遠に続く…と言うことで。
「老子」においても他でもそうなのですが、
翻訳されて日本に入る時に、
翻訳者がどのような思想として理解するか、で意味合いが変わります。
調べてみると、
「正気の歌」は江戸時代中期に浅見絅斎が「靖献遺言」にて伝え、
その後、藤田東湖、吉田松陰、少し時代が現代に近づいて広瀬武夫などが、
彼らなりの「正気の歌」を作っている様です。
私自身も調べて行く中で、
藤田東湖の「正気の歌」、「和文天祥正氣歌」が有名であると知り、
詩に触れてみると、
なるほど、文天祥の境遇と重なる部分も多く、
ほのぐらい牢の中に幽閉された状態であっても、
けして諦めず、強く心を輝かせ、燃やしていた意志に触れる事が出来ます。
藤田東湖は最終的には文天祥の様に死ぬことは無く、
政治の世界に戻って行くのですが、
1855年の安政の大地震で母を庇って亡くなっているので、
その地、藩邸跡である現在の東京都文京区に
「藤田東湖護母致命の処」と記した案内板があり、
また記念碑は移設され、小石川後楽園にあるのだそうです。
こう、藤田東湖の「正気の歌」には歯を食いしばって、
噛み締めて血を流し、グッと睨みつけるような迫力を感じます。
最後まで消えない、目に宿る光こそが正気として感じられるのです。
吉田松陰の「正気の歌」は長州山口県から江戸東京都に向かう…
…今生の別れと思って出頭して行く中で読んだもの。
聖賢雖難企 吾志在平昔
願留正氣得 聊添山水色
聖人、賢人になることもまた難しいが、
私には昔からずっと持っている志がある。
願わくば正気を留め、
(道中、思いを巡らせた地域、また日本の偉人たちの様に)
少し山水の風景に色を添えられると良いな、と。
道中、山口県から東京までの道で景色を眺めつつ、
その地域や思い立つ偉人の功績を思う描写があり、
最後に、自分自身も、もうダメだろうけれども、
後世、残して来た教え子たちが、
吉田松陰を思い出し、また思って、
「そう言う人がいたんだ」と覚えておいてもらえたら、
そこに「正気」があれば良いなぁ…と言う。
そんな風に個人的には読む事が出来るものでした。
風流さがあり、しかし執念はあまり感じないかな…と言う印象。
でもやはり、譲れぬ思いがあり、
その「正気」の不滅を祈る、信じる内容だと感じました。
上條信山先生が「凛冽万古心」を揮毫される際には、
おそらくは、この文言を心に置いてらしたのではないか、と想像しています。
真実は分かりませんが、
心の在り様を強く歌った歌こそ「正気の歌」ですので。
以上、
書道教室のご報告と言葉の解説を申し上げました。
最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとう存じます。
それではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年07月10日
7月8日は、書道教室の開講日でした。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当の宗風でございます。
ただいま、松本市美術館でのワークショップ準備につき、
大わらわと言った所でございまして…。
現状、15名定員の所の8名の入り、「つばなれ」の出来ていない状況で、
少々どころか、とっても焦りつつあります。
どうか、これを読んで下さった方、是非ともお声がけを!
7月20日に一緒にいかがでしょうか~!書道のワークショップなのです。
模造紙にめいっぱい字を書いちゃおうの企画なのです。
なにとぞ、なにとぞー!!
…( ゜д゜)ハッ!
すみません、取り乱しました。
7月13日にも松本市美術館友の会の理事会があり、
その後に、美術館職員さん方との懇親会もあり、
御子柴英遠さんと宣伝も、「我ら欅の森ここにあり!」と…
…宣言するよりも宣伝して来ないといけませんよね。
頑張ります。満員札止めがいちばん嬉しい訳ですので。
時に落語などの演芸の言葉で「つばなれ」とは、
「ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ…」と数えて行って、
「10」で「とお」と読み「つ」が無くなるので、
「つばなれ」と言うだそうです。符丁ですね。
さて、「欅の森書道会」の次回は7月22日となり、
15日の競書の入手日を過ぎておりますので、
これをお持ちになって頂く形になります。
それまで一生懸命に励んで参りましょう。
・
・
さて、それでは各種お知らせごと、日程を見て行きましょう。
松本市美術館の市民ギャラリーの展示スケジュールが更新されており、
以下、掲載されておりました。
( URL: https://matsumoto-artmuse.jp/exhibition/civic-gallery/ )
第14回 欅の森書道展
→2024年10月4日(金) - 2024年10月6日(日)
第42回信州書象展
→2024年11月29日(金) - 2024年12月1日(日)
第65回松本市芸術文化祭参加 松本地区書道展
→2024年10月12日(土) - 2024年10月14日(月)
長野県書道展
→2024年12月13日(金) - 2024年12月15日(日)
そして年明けに毎年の恒例、松本市美術館友の会展があります。
欅の森書道会の総会でもアナウンスありましたが、
今年は賑やかな、大忙しな年になりそうです。
・
・
さて、普段ですとここで条幅課題のお手本を
樋口玄山先生より皆様預かっておいでと存じますので、
言葉の解説などを行うのですが、今月、少し難航しております。
「凛冽たり万古の心」
これを玄山先生が黒板に貼り出して下さっておりますが、
この出典が分からない。しかしながら、
「凛烈萬古存」で、
「凛烈として万古に存す」と言う一節がありました。
冽と列は等しいものとして取り扱って良いとは、検索先にて。
(この良い気の満ち溢れるところ)厳しく(凛冽として)永遠に存在すると言う意味だそうです。1文字違うだけなのですね。
「凛冽」とは、ひとつ「寒気が厳しいさま」、ひとつ「態度、気風、性格が厳格であること、そのさま」だと言います。
「万古」は「遠い昔からずっと」と言う永遠を意味する言葉です。
文天祥の「正気の歌」と言う文章の中にあるものなのですが。
「凛冽万古心」が競書誌「書象」2024年8月号の課題です。
「厳格であれば、その心は永遠に続いて行く」
「厳格さが、心を永遠のものとする」…この様な意味になるのでしょうか。
もう少し調べてみますが、現状はこんなところ、
ご報告できる部分となります。
自分への厳しさ無く、ダラダラゆるゆるで過ごしていて、
それがその後に良い影響となるかどうか…
運が良ければ現状維持?でも、現状維持も実はすごく難しいですよね。
克己、己への厳しさが心を鍛える、人を鍛える。
そんな風に思いますし、信山先生もそう考えて揮毫されたのかも知れませんね。
…と、本日はここまで。
お開きの時間と相成ってございます。
冒頭の写真は7月8日18時過ぎの欅の森書道会前の土手あたり。
夕方に吹く風は心地が良いですよねぇ。
さぁ本日もこの後は書道に勤しもうと思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。