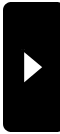2022年12月01日
明日非所求…明日は求むる所にあらず。
・
・
こんにちは、信州塩尻市・欅の森書道会です。
次回の書道教室は12月5日となっております。
2022年11月号の競書誌「書象」の課題提出日です。
昇段、昇級試験があった方は、
おそらくは当日に新たな段級位を教えて頂けると思うので、
競書課題の段級位部分は空白にしてお見えになって頂いて、
当日に書き加える形がよろしいかと存じます。
朧気ですが、細めの筆ペンの用意があった様な…
心配な場合は1本、お持ちになった方が良いやも知れません。
硬筆の場合は、お使いのペンもあった方が良いかも、ですね。
さて、今回は現在取り組んでおられる事と存じますが、
「書象」2022年11月号の基本課題から。
「明日非所求」とあり、これは陶淵明の「游斜川」より。
陶淵明は、陶潜とも。
彼の別の詩には「歳月不待人、歳月人を待たず」と言う、
この時期に特に耳にする一節もありますね。
「游斜川」、「斜川」は地名です。「斜川に遊ぶ」と言うもので、
人生の晩年を憂いながら斜川の景色を眺め、その後半に、
未知從今去:未だ知らず、今よりのち
→ 今より先のことは分からない。
當復如此不:まさにまた、かくの如くなるべきやいなや。
→ 今日の様な、同じようなことが出来るか分からない。
中觴縱遙情:中觴、遙情をほしいままにし
→ 中觴は盃の半ばまで酒を飲む…の意。
遙情は遠く離れた、逸脱した思い。現世を超越する思いを表すとのこと。
忘彼千載憂:彼の千載の憂ひを忘れん
→ 死と言う憂いを忘れてしまおう。
千載はずっと思い続ける、懸案の…と言う意味。
且極今朝楽:しばし今朝の楽しみを極めん。
→ 今を楽しむことにしよう。
明日非所求:明日は求むる所にあらず
→ 明日の事は今考えなくて良いよね。
…と言うもの。憂うものはある。
けれども、明日どうこうと更に憂いでいるよりは、
今をちゃんと楽しんで行こうじゃないか…と、
最初は辛い気持ちがあったが、風景やお酒、客人と楽しむこと、
そうした楽しみの中で、思い直す。憂いを置き去る…と言う詩ですね。
…そう解釈しました。自分なりに、ですが。
実は3月に開催される予定の「欅の森書道展」への作品制作について、
玄山先生へのお手本の依頼、この後半部分の一部をお願いしました。
後半4行の中から「忘彼千載憂」を抜いて。
本来、5文字2行1セットなので抜かない方が良いとは思うのですが、
終わりを意識するからこそ大切なことに気付く…とも思います。
お酒と共に思う気持ちの中で、
憂いも嬉しさも全て飲み込んで、良い心地の今、
今こそ…と思いたい。
…半切、条幅長さについて、14文字前後がベストで、
10では短く、20では多いと言うことで、そうなった…と言う所なのですが。
「欅の森書道展」の為、お手本の依頼がまだの方、
書道教室上のどこかに依頼向けのA4の紙1枚があると思いますので、
是非、ご記入くださいませ。
・
展覧会と言えば、年明けの松本市美術館において、
「第21回美術館友の会 会員作品展」が催されます。
23日の休館日がありますが、2023年1月18日から1月29日まで。
先日の教室で御子柴英遠さんよりお話を頂戴致しました。
出品料は1000円、友の会会員でなければならないので、
年会費3000円が費用として必要ですが、
入会と共に、美術館の企画展の招待券と、
信山先生の作品群も含むコレクション展示の無料観覧が特典で、
…こう言う言い方は良くないかも知れませんが、
「元は取れる」と言うカタチです。
今回から、私、宗風も参加してみたいと思います。
また追加で情報がありましたら、ブログにてご報告致します。
では、本日はここまで。
なかなか課題の出典を追えずじまいでおりましたが、
ようやく書く事が出来る内容になりました。
それでは次回12月5日、年内の最終日は19日となっております。
本日から寒くなるとの事ですので、どうぞめいめい様、ご自愛下さいませ。
欅の森書道会、Web担当の宗風でした。

(画像がないとブログとして締まらないので、
拙作で恐縮ですが、游斜川の一節を書いたものをアップしました。
どなたかお許し頂けるなら、作品などもアップロード出来たら…と思います。
お声がけくださいませ~。)
2022年11月21日
「三喚すれども一應せず」

・
・
こんにちは、信州塩尻市・欅の森書道会です。
本日21日は、11月2回目の教室開講日です。
朝は昨晩から続いて雨模様でしたが、晴れましたね。
どうぞお気をつけて、お集まり願います。
さて、ブログタイトルは競書誌「書象」2022年12月号の「漢字条幅」の課題から。
「三喚不一應」です。
「應」の字はどこかでご覧になったことがあるやも知れません。
いちばん多く目にするのは、
慶応、慶應で、慶応義塾大学の名を見る時…でしょうか。
箱根駅伝とか。
「応」の字の旧字となっております。
この言葉の出典は自分では調べが付きませんでした。
3回わめいても、全く反応しなかった…と言う意味。
「3度」と言う回数は、古来より何かと使われているものでして、
「仏の顔も三度まで」が「二度あることは三度ある」は有名ですね。
アジア圏だけでなく、キリスト教の関係でも、
「今日、鶏が鳴く前に、ペトロ(あなた)は三度わたしを知らないと言うだろう」
…と言う一文があるそうです。
どれにも「三度」、絶対性を持つ言葉に感じます。
1度ならず2度までも、それだけで飽き足らず3度目もあると言う。
この言葉は格言や禅語の様な意味ならば、「集中」を感じますよね。
呼ばれても応えず。
しかしながら、状況によっては師の声、周囲の声に耳も貸さないとも。
はてさて、出典が分からないので好き勝手に申し上げてしまいますが…。
昨晩書いて、とりあえずの3枚、
本日書道教室にて先生に添削して頂こうと思います。
それでは後程。
宗風でした。
2022年11月16日
2022年10月14日
2022年09月15日
競書誌「書象」2022年10月号、到着しています。

こんにちは、塩尻市・欅の森書道会です。
競書誌「書象」2022年10月号、到着しております。
・
先達ての漢字条幅課題「開門月満天」は、「門を開きて月、天に満つ」とのことです。
今月の課題をそれぞれ見てみますと、
基本課題の「掬水月在手」、「水を掬すれば月、手に在り」とし、
この季節に多く目にする課題と思います。
「掬する」は「すくう、すくい上げる」と言う意味で、「きくする」と読みます。
この句の続きには「弄花香満衣」、「花を弄すれば香、衣に満つ」とあります。
唐代の詩人「于良史(うりょうし)」の「春山夜月」からの出典ですね。
すごくロマンチックな詩だと思います。
行書臨書規定(師範・準師範・段位)の中の「實」は「実」の旧字になります。
行書臨書規定(級位)の中の「藐」は解説にもありますが、行書での表現だと少し現代の字形と異なりますね。
…現代の、と言っても初めて見る感覚の字ですけれども。
「藐」の意味は1:かろんじる、さげすむ。2:ちいさい。3:うつくしい。4:遠い、はるか…などの意味を持つ言葉だそうです。
・
第38回読売書法展の作品が掲載されております。
理事である樋口玄山先生の作品と、
「秀逸」に選ばれた池口聖嶽さんの作品です。
・
競書の成績では、
基本課題で、彩紅さん、
研究課題で、素州さん、
古典課題で、涼香さんが写真版に採用されております。
おめでとうございます。
・
・
以上、「書象」2022年10月号から、でした。
次回、欅の森書道会の教室開講日は9月19日となっております。
よろしくお願い致します。
--------------------欅の森書道会、各種情報はこちらから。
https://keyakinomori.naganoblog.jp/
----会の沿革、システムなどなど。各項目へのリンク集となっております。
2022年08月26日
第41回・信州書象展の開催。
こんにちは、信州塩尻市、欅の森書道会です。
速報的に、お知らせを。
また情報が増えましたら都度ご報告して参ります。
来る2022年11月、信州書象会が主催し、
第41回・信州書象展の開催が決定致しました。
場所は松本市美術館です。
開催スケジュールは以下の通り。
2022年11月11日(金)から、13日(日)までの3日間。
11日は、13時から17時。
12日は、9時から17時。
13日は9時から午後4時まで。
(14時頃から作品の批評会、3階の上條信山記念展示室の鑑賞会)
…となっております。
書象会の会員の皆さんは書作に日々打ち込んでおり、
その意気のある作品が一堂に展示される書展になります。
松本市美術館は、上條信山先生の記念展示室もある施設。
そちらで、信山先生から脈々と受け継がれる「信山流」、
書の煌めきをご覧になって頂ければ幸いと存じます。
第41回とあります。
私、このブログを投稿しております宗風の2020年2月のSNSには、
この様な記録が残っておりました。
「5月8日から5月10日まで、第41回信州書象展。2年に1回だそうだ。」
コロナ禍が始まる直前のこと。
冬が明け、春になってコロナ禍に突入し、
開催されないまま本年まで。
ようやくの披露目となり、たいへん喜ばしい心持ちであります。
感染症対策をしっかりと取って、盛会を祈りつつ、
本日はご連絡まで。
追って情報など、手に入り次第更新して行きますので、
またよろしくお願い申し上げます。
以上。
速報的に、お知らせを。
また情報が増えましたら都度ご報告して参ります。
来る2022年11月、信州書象会が主催し、
第41回・信州書象展の開催が決定致しました。
場所は松本市美術館です。
開催スケジュールは以下の通り。
2022年11月11日(金)から、13日(日)までの3日間。
11日は、13時から17時。
12日は、9時から17時。
13日は9時から午後4時まで。
(14時頃から作品の批評会、3階の上條信山記念展示室の鑑賞会)
…となっております。
書象会の会員の皆さんは書作に日々打ち込んでおり、
その意気のある作品が一堂に展示される書展になります。
松本市美術館は、上條信山先生の記念展示室もある施設。
そちらで、信山先生から脈々と受け継がれる「信山流」、
書の煌めきをご覧になって頂ければ幸いと存じます。
第41回とあります。
私、このブログを投稿しております宗風の2020年2月のSNSには、
この様な記録が残っておりました。
「5月8日から5月10日まで、第41回信州書象展。2年に1回だそうだ。」
コロナ禍が始まる直前のこと。
冬が明け、春になってコロナ禍に突入し、
開催されないまま本年まで。
ようやくの披露目となり、たいへん喜ばしい心持ちであります。
感染症対策をしっかりと取って、盛会を祈りつつ、
本日はご連絡まで。
追って情報など、手に入り次第更新して行きますので、
またよろしくお願い申し上げます。
以上。
2022年08月21日
「書象」2022年9月号の課題から。
こんにちは、信州塩尻市、欅の森書道会です。
明日、22日は8月の書道教室2回目です。
お盆を過ぎて、少し涼しくなって来たでしょうか。
それとも雨が多いからでしょうか。
明日、課題を玄山先生に添削、指導して頂くべく、鋭意励んでおります。
その中で、課題について調べてみた部分もありますし、
ほんの少しでもご参考になればと更新です。
【基本】
秋天万山浄
秋天万山浄し、浄でキヨシと読みます。
先月に続き「浄」の字が入っていますので、
より字の本質に迫ることが出来るかも、ですね。
秋の空の美しさを謳った句。
出典は見つけることが出来ませんでした。
漢詩に触れてみると、
春と秋の良い季節を読んだものが多い様に感じます。
【臨規】
之飯。三徑斯絶
化度寺碑の臨書になります。
「徑」の字は「径」の旧字体になります。
「斯」は、日常で見かけるじではありませんが、どこか見覚えがある…と思いました。
「瓦斯」、ガスの当て字に使われていますね。
「斯」は、シ、これ、この、かく…など読み、「此」に通じます。「斯道」なら、この道と言う意味だそうです。
【条規】
蝉聲在高樹
蝉聲高樹に在り、これも出典は調べ切れませんでした。
意味は字の通りですね。
蝉は「ツ」部分が「口ふたつ」になっています。
特に課題は「口」を四角に書かずに「△」で表現されていますね。
聲は「声」の旧字です。
高は…と、【臨規】の課題にある「亭」と同様に「髙」、最初の口が梯子状、旧字体となっています。
・
・
・
以上、
課題についての豆知識的なものになる…のかも?
そんな更新でした。
明日、22日は8月の書道教室2回目です。
お盆を過ぎて、少し涼しくなって来たでしょうか。
それとも雨が多いからでしょうか。
明日、課題を玄山先生に添削、指導して頂くべく、鋭意励んでおります。
その中で、課題について調べてみた部分もありますし、
ほんの少しでもご参考になればと更新です。
【基本】
秋天万山浄
秋天万山浄し、浄でキヨシと読みます。
先月に続き「浄」の字が入っていますので、
より字の本質に迫ることが出来るかも、ですね。
秋の空の美しさを謳った句。
出典は見つけることが出来ませんでした。
漢詩に触れてみると、
春と秋の良い季節を読んだものが多い様に感じます。
【臨規】
之飯。三徑斯絶
化度寺碑の臨書になります。
「徑」の字は「径」の旧字体になります。
「斯」は、日常で見かけるじではありませんが、どこか見覚えがある…と思いました。
「瓦斯」、ガスの当て字に使われていますね。
「斯」は、シ、これ、この、かく…など読み、「此」に通じます。「斯道」なら、この道と言う意味だそうです。
【条規】
蝉聲在高樹
蝉聲高樹に在り、これも出典は調べ切れませんでした。
意味は字の通りですね。
蝉は「ツ」部分が「口ふたつ」になっています。
特に課題は「口」を四角に書かずに「△」で表現されていますね。
聲は「声」の旧字です。
高は…と、【臨規】の課題にある「亭」と同様に「髙」、最初の口が梯子状、旧字体となっています。
・
・
・
以上、
課題についての豆知識的なものになる…のかも?
そんな更新でした。
2022年08月15日
書象誌、届いています。

こんにちは、信州塩尻市・欅の森書道会です。
競書誌「書象」2022年9月号、教室のいつもの棚に届いておりました。
今月は巻頭及び条幅随意の課題が、樋口玄山先生がご担当されております。
競書の成績では、
隷書条幅の部で、白水さん、弦象さん、
条幅随意の部で、光水さん、
楷書段位の部で、赤木さん、
仮名段位の部で、赤木さんが、それぞれ写真版に優秀作品として選ばれております。
おめでとうございます!
次回、欅の森書道会の教室は22日となっております。
それではまた当日に。
以上、連絡でした。
2022年07月21日
心如流水浄、基本課題より。

こんにちは、あるいはこんばんは。
欅の森書道会です。
写真は書道教室の日だけ使用を許して頂いている
地域の公民館から教室に向かって歩いた土手にある向日葵です。
季節の移ろいは早いもので、夏の盛りが差し迫っているのだなぁと感じます。
さて、本日は競書誌「書象」2022年8月号、
「基本」課題にあります「心如流水浄」と言う言葉について。
心、流水の如く浄かなり。
調べてみますと出典は見つからなかったのですが、
松本市美術館、平成27年9月8日(火)~平成28年1月17日(日)の
上條信山記念展示室に、57.7×34.6cmサイズの作品として掲げられた記録がありますので、
私達が見ている書象誌の条幅作品とは別にありそうです。
普段私たちが用いる「きよらか」は、
「清」が一般的ではないでしょうか。「浄い、きよらか」はなかなかお目に掛かりません。
一説に、物理的に「清」、で精神的に「浄」を用いると言い、
神社や寺院に関わる部分で「浄」と言う言葉が多いですね。
出典も、そう言った部分から禅語、経典にあるやも知れません。
しかしながら、漢詩を眺めてみますと「流水」と言う言葉は多く、
詩人が絶え間なく流れる水の景色、
時として清く、時として濁り、また暴れもする…
心情を様々なカタチで乗せている言葉にも思います。
蘇軾の「謝民師推官与書」に出典があるとされる「行雲流水」と言う言葉も、
とても有名ですし、学生書道のお手本にもよく用いられますね。
普遍的に動き続ける、しかし常の清らかさの象徴。
「基本」課題をお稽古される際に、また感情が加わりますと趣も違って来るかも?
どうでしょうか。
それでは今回はここまで。
宗風でした。
--------------------欅の森書道会、各種情報はこちらから。
https://keyakinomori.naganoblog.jp/
----会の沿革、システムなどなど。各項目へのリンク集となっております。
2022年07月15日
競書誌「書象」、8月号が届きました。

競書誌「書象」、2022年8月号が教室に届けられていました。
碧空さん、赤木さんが写真版に選ばれておりましたね。
おめでとうございます!
--------------------欅の森書道会、各種情報はこちらから。
https://keyakinomori.naganoblog.jp/
----会の沿革、システムなどなど。各項目へのリンク集となっております。