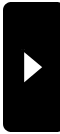2025年05月16日
第64回書象展の結果発表と「書象」2025年6月号の到着について。

こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市、欅の森書道会のお馴染みウェブ担当の宗風です。
皆様のお手元に届いておりますでしょうか…の噺が2件ほどございます。
ひとつは連絡網でもご案内があったかと存じますが,
月例の競書誌、新しいものが届いておりますすので、
お受け取りを是非どうぞ…と言うご連絡がひとつ。
もうひとつは吉例、書象展の結果が郵送されて来ておりましたね。
奨励賞に御子柴さん、書象賞に上條さん、
特選に奥原さん、百瀬涼香さんが選ばれております。
おめでとうございます!
Posted by 欅の森書道会 at
19:03
│Comments(0)
2025年05月13日
5月12日は,欅の森書道会5月1回目の研修日でした+条幅課題「有何比松柏」について。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会のウェブ担当、宗風でございます。
お馴染み様です。
ゴールデンウィークを挟みまして、普段の2週ではなく3週ぶりの研修日となりました。
何だか、たった1週であったとしても「久し振りだ」と感じてしまうものですね。
まだまだ寒さの残る季節だった4月から、
朝晩に少し気温は下がりますが、新緑が目に鮮やかに、
暑い季節を予感させる風景になって参りました。
端午の節句、5月5日が暦の上では立夏でありまして、
普段ですと「暦の上では夏とは言っても…」なんて四季時期に口々現れたりいたしますが、
どうでしょうか。まぁまぁ「立夏」のような雰囲気を感じるのは、
それは温暖化由来だからこそ良いとは言えないのでしょうけれど、
季節の巡りを感じたりするものですね。
次回は5月26日の予定となっております。
次の競書は5月15日頃の到着となっておりますので,
この課題に取り組んで、またお会いいたしましょう。
昨日12日,後半の部は賑わっておりましたね~。
月例の競書の〆日でもあり昇段昇級試験の〆切でもあり。
季節が良くなったからこその明るさもあったんじゃないかなぁ、などと感じます。
トピックスとしては、
6月23日の総会が目下、
私達、欅の森書道会としては予定としてありますね。
総会があり、添削の場所も普段と異なりますので、ご予定ください。
・
・
ちなみに昨晩は教室の風景を写真に撮り忘れましたので、
信州中野市・一本木公園のバラの写真で、ブログの冒頭を飾りつけております。
ご縁あってライフワークのようなもので、
宗風、SNSにバラの写真を1日1枚ずつ投稿して何年も…になります。
その中から1枚と言ったかたち。
5月24日から毎年恒例のバラ祭りが催されますので、
出掛けて行って1年分の写真を撮る予定でおります。
・
・
さて、毎度恒例の競書誌「書象」の課題の中から、
取り上げられた語句の解説を行いたいと存じます。
これから取り組む2025年6月号の条幅課題はこちら。
「有何比松柏」の5字。
AI技術なんかも使ったりして検索を掛けてみましたが、
出典を見つけることができませんでした。
書き下し文もピタッと来るものが分からず、
おおよその意味は「松柏に何を比べられるだろうか」と言う意味だと考えます。
松や柏と言う堅固であり常緑による長寿健康の意味も含む字、また樹木。
古来よりその姿も含めて縁起の良いもの、壮健である様に用いられていますよね。
これと何が比べられよう、つまりは「とても美しい!」と言いたい。
そんな一句だと思います。それこそ漢詩にありそうなのですが。
ちなみに松の常緑ぶりは普段からもご案内かと存じますが、
一般に「柏」と言えばナラやクヌギのようなブナ科の仲間であり、
これは落葉のある木ですから常緑樹ではありません。
しかしながら、漢詩や中国文学の中では「柏」を指して、
常緑樹のヒノキやスギを表す場合もあるのだそうです。
「堅固」のような「かたい×かたい」と、同じ意味を重ねて作る言葉として、
きっと「松柏」は一緒くたになっていると思うので、
今回の詩の「松柏」は青々とした緑を思い浮かべて良いのだろうな、と考えています。
李白に「松柏本孤直 難為桃李顔」と言う詩の一部があり、
松柏は孤高であり、桃李にはなれない…と言う意味で、
松柏、常緑への憧れ、絶対性を感じますね。
李白の感じた孤高さこそ「有何比」の今回の言葉に通じている、と感じます。
何と比べられようか、何と比べれば良いのだろう、と。
…と、こんなところでちょうどお時間となっております。
それでは本日はここまで。
書道をまた励んで参りましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年04月30日
御子柴さん,松本市美術館友の会の演題を揮毫す。
・
・

こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、ウェブ担当の宗風です。
次回の書道教室は少しいつもの2週間よりは間があきまして,
5月12日となっております。
競書や昇給昇段試験,お月謝の収納日など,
ゴールデンウィーク明け,様々重なっている日となっておりますので,
よろしくお願いしつつ,
さて,本日も一席のお付き合いを願っておきます。
気楽なところで,一生懸命…と言うことです。
・
・
毎年恒例のことですが,
上條信山先生の常設展示もある松本市美術館,
この「友の会」の総会が4月20日に催されました。
友の会の総会と毎年、松本市美術館にまつわる講演会が計画されます。
今年は松本市美術館の館長小川稔さんの講演でした。
折しも大阪万博が開催されておりますが,
万博と博覧会,美術展にある密接な関係性,
また松本市美術館だけでなく茅ヶ崎の美術館の館長でもある小川氏による,
信州と茅ヶ崎を繋ぐ美術の話などの内容でした。
美術史として,非常に興味深かったです。
松本城を残すために市川量造が1873年(明治6年)「筑摩県博覧会」を開かなければ,
今の松本城は無い…そうでした,そうでした。
その話も思い出しました。
人が脈々と繋いで来ている文化、その活動を大いに感じられる講演でした。
美術とは人が形作っているものである、と。

昨年に引き続き,松本市美術館友の会の副理事である御子柴英遠さんが,
今年も演題を揮毫し,ご活躍されておりましたので,ご報告いたします。
書道の面では,
松本市美術館は全国的には珍しいはず…
書道作品を近代美術として捉えているのだそうで,
その点では茅ヶ崎や寒川に縁のある井上有一氏のお話もありました。
興味を持ったので調べてみると,
「井上有一全書業」と言う作品集は相当なものの様で,
中古売買の場でもセットで最低でも40万円から買い取り,高ければ80万円…
書道の作品集がそれと言うのは、凄いなと思ったりなんかもする訳でして。
松本市美術館の開館からメモリアルな年が近いのだそうで,
美術も書道も何かしらの盛り上がりのある動きを目指しているようです。
もう企画は動いているんだろうな,と感じました。
上條信山先生も関わる松本市美術館。
欅の森書道展も松本市美術館。
今後とも深く関わって行くことになろうと思います。
そんな友の会の一席にて,本日はおしゃべりいたしまして,
ちょうどお時間と言うことです。
それではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
・

こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会、ウェブ担当の宗風です。
次回の書道教室は少しいつもの2週間よりは間があきまして,
5月12日となっております。
競書や昇給昇段試験,お月謝の収納日など,
ゴールデンウィーク明け,様々重なっている日となっておりますので,
よろしくお願いしつつ,
さて,本日も一席のお付き合いを願っておきます。
気楽なところで,一生懸命…と言うことです。
・
・
毎年恒例のことですが,
上條信山先生の常設展示もある松本市美術館,
この「友の会」の総会が4月20日に催されました。
友の会の総会と毎年、松本市美術館にまつわる講演会が計画されます。
今年は松本市美術館の館長小川稔さんの講演でした。
折しも大阪万博が開催されておりますが,
万博と博覧会,美術展にある密接な関係性,
また松本市美術館だけでなく茅ヶ崎の美術館の館長でもある小川氏による,
信州と茅ヶ崎を繋ぐ美術の話などの内容でした。
美術史として,非常に興味深かったです。
松本城を残すために市川量造が1873年(明治6年)「筑摩県博覧会」を開かなければ,
今の松本城は無い…そうでした,そうでした。
その話も思い出しました。
人が脈々と繋いで来ている文化、その活動を大いに感じられる講演でした。
美術とは人が形作っているものである、と。

昨年に引き続き,松本市美術館友の会の副理事である御子柴英遠さんが,
今年も演題を揮毫し,ご活躍されておりましたので,ご報告いたします。
書道の面では,
松本市美術館は全国的には珍しいはず…
書道作品を近代美術として捉えているのだそうで,
その点では茅ヶ崎や寒川に縁のある井上有一氏のお話もありました。
興味を持ったので調べてみると,
「井上有一全書業」と言う作品集は相当なものの様で,
中古売買の場でもセットで最低でも40万円から買い取り,高ければ80万円…
書道の作品集がそれと言うのは、凄いなと思ったりなんかもする訳でして。
松本市美術館の開館からメモリアルな年が近いのだそうで,
美術も書道も何かしらの盛り上がりのある動きを目指しているようです。
もう企画は動いているんだろうな,と感じました。
上條信山先生も関わる松本市美術館。
欅の森書道展も松本市美術館。
今後とも深く関わって行くことになろうと思います。
そんな友の会の一席にて,本日はおしゃべりいたしまして,
ちょうどお時間と言うことです。
それではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年04月22日
4月21日は4月2回目の研修日でした+各種お知らせ+「澹澹長江水」について。
・
・

こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市,欅の森書道会のウェブ担当,宗風です。
お馴染みさまでございます。
本日も気楽なところで一生懸命…と言うことです。
昨晩も欅の森書道会,教室は賑わっておりました。
書象展への出品が終わり,今度は昇給昇段試験が掛かり,
また作品制作が無いからこそ,日々のお稽古では,
競書にて基本を更に深めて行くような。
春の催し物,お誘い多い時期となって,
皆々様,お忙しくされているのではないでしょうか。
朝晩の冷え込みと日中の暑さとの寒暖差も激しくなっておりますので,
どうぞご自愛しつつ,楽しんで行こうではありませんか!
…なんてンで,そう言う時節の挨拶といたしたいところであります。
・
さて,次回の欅の森書道会の研修日は5月に入ります。
5月12日となりますが,ここにご連絡事項がありますので,
要注意,となります。
5月12日は競書の作品の提出日です。
併せて,昇給昇段試験の提出日ともなります。
その次が5月26日と,20日の〆日を過ぎますので,
上記の予定となりますことをご承知おきください。
よって,昇給昇段試験の受験料の納入も5月12日となります。
ご用意をお願いいたします。
また月々のお月謝についても,
6月の欅の森書道会の総会を前に,会計監査が行われますので,
5月12日に必ずお持ちいただくようにお願いいたします。
また6月2日には欅の森書道会の理事会が18時から。
この時間は添削を一旦止めて,理事会の時間を持ちます。
教室そのものは開いておりますので,
中で待つこともできます。
6月23日(月)は,いつもの広丘吉田の欅の森書道会の教室ではなく,
総会開催のため,松本市の燦祥館にて16時から添削となっております。
添削会終了後に総会,そして懇親会が予定されております。
ご承知おき,またそれぞれ参加か不参加については,
教室の名簿に記入するか,ご連絡をお願いいたします。
以上,ご連絡事項でした。


教室の風景をトップに配置しましたが,
ご厚意にて車を置かせていただいている,
公民館からの道すがら,
川べりの風景は好きで,その写真をば。
良い風が吹く,また夕暮れの美しい光に出会える季節になりましたね。
・
・
さて今回も課題に用いられている言葉,
この出典や意味などを解説いたしまして,
お開きとさせていただきます。
競書誌「書象」2025年5月号の課題から,
[澹澹長江水],「澹」は「タン,しずか,あわい,うすい」と読む,とのこと。
「しずか,おだやか,やすらか」と言った意味だそうです。
書き下し文では「澹澹(たんたん)たる長江の水」となります。
長江については幾度となく漢詩の世界では登場しますね。命の源、また文化の源。
大河,その流れが静かである様を表現しております。
この出典を検索してみましたが,昨今のAIを含めても探してみて,
発見できませんでした。AIが言うには,課題の為に作られた言葉、句の可能性もある…とのこと。
本題とは関係ありませんが,この「澹」と言う字によく似て,
サンズイではなくリッシンベンの「憺」の方が,どうでしょう…
「見たことがある漢字だな」と思いました。
小説など読んでおりますと「惨憺たる光景」と言う様な使われ方をしますね。
「憺」には「惨」と言う字と重ねるにふさわしい,
「おそれ,おそれさせる」と言う意味もありますし,
「澹」の持つ「あわい,うすい」意味は無いものの,
同じく「しずか」と言う意味があって,
パソコン上の変換でも「サンタン」は「惨憺」と「惨澹」がどちらも候補になります。
意味としても問題ないですものね。
こうして字や句について調べておりますと,
既存の知識に更に深みが増すように感じます。
更に調べると「淡」の旧字として「澹」が使われることもあるのだとか。
ただし「しずか」と言う意味を「淡」は持ちませんから,「使われることもある」です。
書象展の作品で素風さんが「恬淡(てんたん)」を揮毫されておりましたが,
つまりは「恬澹」でも良いと言うことですね。
「あっさりとしていて,名誉・利益に執着しないさま」を言うそうです。
…と言うことで,本日の一席,ブログはここまで。
ちょうどお時間となったようでございます。
それではまた次回。
5月になればまた「工芸の五月」で松本が賑わいますね。
書道と言う文化もまたどこか広がりが生まれれば良いのですが。
それでは。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年04月14日
松本市美術館友の会へのお誘い。

・
・
宣伝させてくださいませ。
こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会のウェブ担当,宗風でございます。
本日は欅の森書道会にも多数参画していただいている,
「松本市美術館友の会」についてお喋りさせていただきます。
御子柴さんと私,宗風は友の会の理事に任命されておりまして,
友の会員を増やすための活動をせねばなりません。
このブログの利用も然り。
4月から松本市美術館も新年度となり,
昨今の世情によって常設展,コレクション展示への入館料が値上げになりました。
これまでの一般410円から電子チケットで700円,美術館窓口ならば800円となります。
その代わり,「中学生以下及び70歳以上の松本市民が無料」であったところに,
「高校生以下及び70歳以上の松本市市民が無料」と範囲が拡大されています。
企画展は都度値段が設定されますから,こちらも上がってはいるのでしょう。
世知辛い世の中…と嘆くことはありません。
皆さんも,美術館友の会にご入会なさいますと,景色はまた違って見えるはずです。
・
松本市美術館友の会へのご入会に関して,
資格は特にありません。
どなたでも入会できます。美術の腕がある必要もなく、
美術が好き、美術館の展示をお得に見たい!…そんなカタチで大丈夫。
お申込みについては,美術館開館中に代表番号へのお電話でお願いいたします。
「友の会に加入したいのですが」と言っていただければ案内がございます。
常設で係員はおりませんで,中の方のどなたかが対応してくださいます。
・
さて。
ここで何よりお伝えしたいのが,年会費と特典の関係性です。
世情を加味すれば,とてもお得になった…とも言えるかと。
年会費は一般で3000円となっております。
特典として美術館の招待券のプレゼント,
発行される会員証にて常設展の観覧,
ワークショップなどイベント参加費の割引,美術館の売店の割引などがあります。
実は一般会員を例に取った場合,
招待券の配布枚数が5枚から4枚へと減っております。
けれども,だけれども,
結果的に特典はグレードアップしていると言うことを,
松本平に響き渡るくらい大きな声でお伝えしたい。
☆昨年までは。
1000円以上の招待券5枚,410円の常設展を4期分として4回見るなら,
5000円と1640円で6640円,年会費分を差し引いて3640円の利。
…とは言え,実際に企画展は1300-1800円くらいでしょうか。
これでもかなりお得なんです。
☆今年からは。
1000円以上の招待券4枚,800円の常設展を4期分として4回見るなら,
4000円と3200円で7200円の年会費で4200円の利。
つまりは年に4回変わる常設展分は据え置きだった…と言うことです。
すごくありがたい。僕はすごくありがたいと思っています。
美術館友の会に入ったことで,美術館との繋がりが増えて,
年に10回ほどは出掛ける様になりました。もっと多いかも。
信山先生との対話…とはおこがましいかも知れないけれど、
肉筆を肌で感じられる,何度も何度でも,軽くフラッとお出掛けできる。
すごく嬉しいと感じているのです。
自分みたいに暇さえあれば信山先生の作品を学びに出掛ける方,
草間彌生さんの世界に1ヶ月に1回は没頭したい…なんて方は,もうお分かりですね?
かつワークショップに出れば,他の方より得が多い訳です。
あと忘れてはいけないのが市民ギャラリーの存在です。
常に開催されている訳ではありませんが,
何かしら市民ギャラリーは利用されており,
多く入場料無料で観覧できるイベントばかりです。
何度も美術館に来て,何度も常設展を楽しみ,多種多様なアートに触れる。
実に素晴らしい!素晴らしいとは思いませんか!
…と言う宣伝内容でございました。
このブログのリンク記事,ドシドシ拡散して下さって結構でございます。
どうぞ美術館利用者様が増えて増えて,
もっと賑わいますように。
そんな祈りを込めつつ,本日の一席はここまでとさせていただきます。
それではまた。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
-------------------------------
宗風、2025年7月21日に3度目のワークショップ担当となります。
内容は昨年と同じ。同じにしました。
自由に筆を使って大きく書く!
もうこれ!これが自分も楽しいんです。
模造紙に創意工夫で書くと言うのは,無限の可能性がありました。
それを私自身も見たいので。
ご参加をお考えの方は,
今から作品の案を練っておいてくださいませー。
よろしくです!!
Posted by 欅の森書道会 at
19:17
│Comments(0)
2025年04月08日
4月7日は欅の森書道会4月1回目の研修日でした+「書象」2025年5月号課題「日暮隄上立」について

・
・
こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会,お馴染みウェブ担当の宗風です。
本日もいっぱいのお運びさま,誠にありがとう存じます。
気楽なところで一生懸命…と言うことです。
終いまで,どうぞお付き合いのほどを願っておきますが…。
さて。
新年度が始まり,春の全国交通安全運動が始まりましたね。
今朝も朝から白バイとすれ違いました。
シートベルトはしている,スマホはもちろんカバンの中,
何も悪いことをしていなくても,
でもやっぱり何だか怖い…なんて言うのは、
皆々様,共通の心情ではないかなぁ,なんとは思います。
日中は暖かくなりましたですねぇ~。
朝晩は,やれ冬の再来かと言うくらい寒くも感じるのですが,
はて温度計を見てみると氷点下でもなかったりして,
寒く感じはしていても,春になったんだと,そう思う次第でございます。
4月7日は,欅の森書道会の4月1回目の研修日でした。
池口さんがお見えにならないせいか,
ちょいと静かな教室でしたね。やっぱり居て下さらないと寂しいですね。
樋口玄山先生が膨らんだ封筒を二木さんに手渡しておいででした。
「更にいくつも書いて来て,すごい方だな」と。
書象展の作品だったのでしょう。その意気を買っておいででした。
そんな玄山先生も無事にお戻りになられたでしょうか。
折しもETCがえらいこっちゃ,未曽有の大問題となっており,
欅の森書道会ですと,
そう,我らが玄山先生がモロに影響を受ける訳でして。
信州にお見えになる際は,ちょいと不安もありながら,
途中のSAなどで情報を得ながらお出でになりつつ,
特段,長い待ち時間などの被害を受けることなくご到着されたそうですが,
さて,お戻りはどうでしょうか。
お疲れもあると存じますので,穏やかに過ごされると良いなと思います。
4月7日は競書の提出日ともなり,
皆々様の意気ある作品が集まって旅立って行きました。
昇段昇級試験が今月,来月とありますので,
今月号の漢字条幅課題と臨書規定【行書】,
来月号の隷書条幅課題,臨書規定【楷書】,仮名,硬筆が対象になります。
師範を目指して励んで参りましょう。
ご連絡として以下の掲示がありました。
総会の関係でお月謝の集金日に指定があります。
5月は教室が12日と26日にありますが,
12日のみ、お月謝を集金する形となります。
以上,ご連絡などなどでした。
・
・
さて例によって,
玄山先生から条幅課題のお手本を頂戴いたしました。
今回は「日暮隄上立」とあります。
「隄」は見慣れない漢字ですね。
「堤」と同義で,漢字検定上も「配当外」の字なのだとか。
読みはテイ,つつみです。
この一句が含まれる漢詩は清代の儒学者「汪 中(おう ちゅう)」の「大堤曲」です。
原文はこちら。
東風吹江水
花開照顔色
相思人未歸
日暮隄上立
以上です。書き下し文では次のとおり。
東風吹江水: 東風,江水を吹き
花開照顔色: 花開いて,顔色を照す
相思人未歸: 相思えども,人,未だ帰らず
日暮隄上立: 日暮れて,堤上に立つ
歸は帰の旧字です。
東風とは春風のこと。
意味を追うと,このように。
春風が川の水面に吹き、花は咲き,鮮やかに目に映る。
しかし,思い人はまだ帰って来ない。
日が暮れて、堤の上に立つ。
前半は春の陽気,今のような信州も桜が咲き始めていますよね。
杏や梅ももっと早くに。
氷は解け、川は水かさが増し,緑が輝き始める,
その中でも大切な人がまだ帰って来ないと言う境地。また心情の対比。
きっとまだ来ないのだろう。
でも,ずっと帰って来ると信じて堤の上にて待つ。
そんな意味になります。
皆さんのお手本はどうか…が分かりませんが,
玄山先生のお手本,特に上と立にはカスレがあって,
どこか雰囲気があるように思います。
この一句に含まれる意味を表現したような…
そんな心持ちもいたします。
冬が明けるを待ち、
また新たな一年を迎える方も多い季節でございます。
今月号も是非とも頑張って参りましょう。
…と言ったところで,本日はここまで。
ちょうどお時間となった様です。
それではまた次回。
次回…ええ、松本市美術館友の会の記事を,
ひとつ用意しておりますので、そちらの更新となりますが。
宣伝ですが。
ともあれ。
では,改めましてここまでといたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。

2025年04月03日
春つくし

こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市・欅の森書道会,ウェブ担当の宗風でございます。
いよいよ4月7日が迫って参りましたね。
何の日か…と申しますと,いつもの書道教室がございます。
それだけではありますが,それをいつもどおりに,
春を迎えるように,同じように出掛けられる…と言うのは,
実はひとつの幸せなことでございます。
もちろん,そうでもない方も当然にお見えになる訳で,
是非とも来年こそはいやいや,“そうでない”ことを解決なさって,
であれば,次の風物詩にお会いできれば何よりじゃないか,とは,
常々感じ入るところです。生きてこそ,会ってこその人生ですから。ええ。
また必ずお会いしたい方は,皆々様どなた様にもございましょう。
さて,本日も一席を語るようにお付き合いを願っておきますが…。
・
書道教室の研修日がある週は、これを題材にしてブログをしたためますが,
無い週ともなると「さて,どうしようか」と考える訳です。
我が家の白文鳥アイドル,ピーちゃんの話であれば,
延々と語ることもできようと言うものですが。
春なので,春めいたものを。そんな風に考えます。
頭にタイトル、ちょこんと乗せておりますが,
「春つくし」は、「春,土筆」ではなくて,「春尽くし」と言う,
そんなご趣向でいかがでしょうか。
さる3月30日に信州木曾郡木曽町の木曾文化公園文化センターにて催された,
「第6回 よらまいか寄席」に出掛けて来ました。
立花家橘之助師匠がお馴染み「両国風景」をご披露なさって…
両国橋の川開き,縁日風景の賑やかで文化の香がする,
たいへんに結構なものを一節、ご披露なさいました。
この歌の中に「茶尽くし」と言う言葉遊びが含まれています。
「八丁堀の客人が鎌倉河岸から屋根船で…」と言うところを,
「茶っちょうぼりの,茶くじんが,茶まくらカシから,茶ねぶねで…」と,
言葉の一部を「茶」に変えて行くと言う言葉遊びなんですね。
寄席や,もしかするとお座敷,それこそ屋形船で従来は披露されていたのでしょうか。
今回はこれにちなんで,「春」と付く言葉をいくつか紹介してみようかな,
そう思ってございます。
書道を始めた際に,いろんな言葉を調べました。
その一覧からズバッとコピーアンドペースト,貼り付けてまいります。
「一華開五葉 結果自然成」
「いっけごようをひらきてけっかしぜんになる 」
「花開天下春」
「はなひらきてんかのはる 」
「世尊拈一枝花 迦葉微笑」
「せそんいっしのはなをひねり かしょうみしょうす」
「一枝常発十州春」
「いっしつねにはっすじゅっしゅうのはる」
「一地処生 一雨処潤」
「いっちしょしょう いちうしょじゅん 」
「羽衣舞春風」
「はごろもしゅんぷうにまう」
「雨余春暁」
「うよしゅんぎょう」
「雲門一字花」
「うんもんいちじか」
「春色太平多」
「しゅんしょくたいへいおおし 」
「春色満乾坤」
「しゅんしょくけんこんにみつ 」
「春柳鴬」
「しゅんりゅうにうぐいす 」
「春色向晩 落花満地」
「しゅんしょくくれにむかい らっかちにみつ 」
「山花咲鳥歌」
「さんかちょうかにさく 」
「山花映水紅」
「さんかみずにえいじてくれないたり 」
「山桜火焔輝 山鳥歌声滑」
「さんおうかえんかがやき さんちょうかせいなめらか 」
「一樹春風千万枝」
「いちじゅしゅんぷうせんまんのえだ 」
「一樹梅花」
「いちじゅのばいか 」
「春風接人」
「しゅんぷうひとにせっす 」
「春風以接人 秋霜以慎自」
「しゅんぷうもってひとにっせし,しゅうそうもってみずからをつつしむ 」
「春風去古心」
「しゅんぷうこしんをさる」
「春風牛歩遅」
「しゅんぷうぎゅうほおそし」
「春風佳気多」
「しゅんぷうかきおおし」
「春風花草香」
「しゅんぷうにかそうかんばし」
「春草芳」
「しゅんそうかんばし」
「春風入寿杯」
「しゅんぷうじゅはいにいる」
「春潮満々将来宝貝」
「しゅんちょうまんまんとしてほうばいをしょうらいす」
「春暖青牛臥」
「はるあたたかにしてせいぎゅうふす」
「春逐鳥声開」
「はるはちょうせいをおってひらく」
「春暖花更新」
「しゅんだんはなさらにあたらし」
「春色無高下 花枝自短長」
「しゅんしょくこうげなく かしおのずからたんちょうあり」
「春光日々新」
「しゅんこうひびあたらなり」
「春水澄」
「しゅんすいすむ」
「春酒介寿」
「しゅんしゅはじゅをたすく」
「春柳鶯」
「しゅんりゅうにうぐいす」
「春和景明清」
「しゅんわけいめいにきよし」
「春水満四沢」
「しゅんすいしたくにみつ」
「春生百福觴」
「はるはしょうずひゃくふくのしょう」
「春声先水響」
「しゅんせいはみずのひびきをさきとす」
「春宵一刻桜」
「しゅんしょういっこくのさくら」
「桜花無尽蔵」
「おうかむじんぞう」
「花雲万里去来」
「かうんばんりにきょらいす」
「花影重」
「かえいおもし」
「花何処求行」
「はな いずれのところにかもとめゆかん」
「柳緑花紅真面目」
「やなぎはみどり はなはくれない しんめんもく」
「花間笑語声」
「かかんしょうごのこえ」
「花鳥楽風月」
「かちょう ふうげつをたのしむ」
「花朝月夕随時楽」
「かちょうげっせき ずいじたのしむ」
「花和万友清」
「はなはばんゆうにわしてきよし」
「春霞掛秀峰」
「しゅんかしゅうほうにかかる」
「春岳」
「しゅんがく」
「春山繁春月明」
「しゅんざんしげり しんげつあきらか」
「春坐天地 尽只茶一碗」
「はるはてんちにざして ただちゃいちわんをつくす」
「春山青春水碧」
「しゅんざんあおく しゅんすいみどりなり」
「春来草自生」
「はるきたらば くさおのずからしょうず」
「春来百花枝端上」
「はるきたりて ひゃっかしたんにのぼる」
「春風百花舞」
「しゅんぷうにひゃっかまう」
「桃花千歳春」
「とうかせんざいのはる」
「桃花流水杳然去」
「とうかりゅうすい ようぜんとしてさる」
「桃花笑春風」
「とうかしゅんぷうにえむ」
「三月鶯花」
「さんがつおうか」
「笑語桃花酒」
「しょうごとうかのさけ」
「一花笑春風」
「いっかしゅんぷうにえむ」
「万里百花春」
「ばんりひゃっかのはる」
「桃花三千歳」
「とうかさんぜんさい」
「桃花似錦柳如煙」
「とうかにしきのごとく やなぎはけむりのごとし」
「桃紅照流水」
「ももはくれないにして りゅうすいをてらす」
「桃水滴々」
「とうすいてきてき」
「出門天地春」
「もんをいづれば てんちのはる」
「陽春布徳沢」
「ようしゅんとくたくにふす」
「花発多風雨 人生足別離」
「はなひらけばふううおおし じんせいべつりおおし」
「梅花一彩春」
「ばいかいっさいのはる」
「梅一点梅花蕊 三千世界香」
「うめいってんばいかのずい さんぜんせかいかんばし」
「梅花和雪香」
「ばいか ゆきにわしてかんばし」
「梅仙飛道香」
「ばいせんとびて みちにかおる」
「梅花雪裏香」
「ばいか せつりにかおる」
「落花随流水」
「らっか りゅうすいにしたがう」
「落花埋古径」
「らっか こけいをうめる」
…などなど。
一部を変えただけ…なんてものも多かったりします。
春は何にせよ,辛く厳しい冬を越えて訪れるものですから,
誰しもが喜びに満ち,お浮かれになる季節でございます。
よって,漢詩の中にも多く読まれている言葉のひとつですね。
お気に召したもので一筆取ってみてはいかがでしょうか。
…と,それではちょうどお時間となったようです。
本日もお付き合いいただきまして,
誠にありがとうございました。
それではまた来週,欅の森書道会,
研修日の後,お会いいたしましょう。
それでは。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年03月26日
3月24日は欅の森書道会の3月の研修日2回目でした+仮名の課題の紹介を。
・
・

こんにちは、あるいはこんばんは。
いつもの写真を撮り忘れましたので,
我が家の白文鳥アイドル,ピーちゃんの画像で失礼いたします。
本文とは全く関係がありません。
さて。
3月24日の信州塩尻市・欅の森書道会、
夕方過ぎから予報通りと言えば予報通りなのですが,雨になりましたですねえ。
ちょうど書象展の作品制作の〆切り日。
大切な…しかし水にとことん弱い紙での作品を抱える私達には,
いやはや恵みの雨とも言えども、脅威でもありました。
前半組の方々は,清々しい春の陽気で何よりだったのではないでしょうか。
気候に変化があって体調もおぼつかなくなっていたりもいたしますが,
共に励んで参りましょう。
ご挨拶が遅れました,お馴染みウェブ担当の宗風でございます。
本日も気楽なところがよろしいんじゃないか,という所ですが、
一生懸命,申し上げることにしておりますンで,
どうか最後までお付き合いくださいませ。
さて,そんな訳でございまして。
毎年恒例,1年1回の挑戦ですよね。
最大の社中展となります「書象展」の〆切が24日となっておりました。
意気のある作品が持ち込まれ、
熱の有る樋口先生の指導、選定を経て、
落款印を捺してもらって旅立って行きました。
皆さま、本当にお疲れさまでした。
そして,より良い結果となりますよう祈ります。
・
・
次回の欅の森書道会の研修日は,4月7日となっております。
競書誌「書象」2025年4月号の作品提出日となっておりますので,
続けて…とは相成っておりますが,作品をお持ちください。
その次は21日ですね。ここでは5月号の添削が予定されております。
普段ですと,ここで【基本】の課題,
その一句を含む漢詩の紹介をするところなのですが,
今回の「送君還舊府」は以前に課題になりましたね。
ブログ記事だと2024年9月に紹介しております。
( https://keyakinomori.naganoblog.jp/e2799585.html )
この時は【研究】課題でした。
さかのぼってみると漢字条幅で2021年8月号の課題だった様です。
確か「旧」の旧字の「舊」を,私が初めて知ったのが,この課題だったと思います。
これはこれで確認していただくとして。
では仮名の課題を少し見てみましょう。
「はるののに 春(す)みれつみ尓(に)と 来しわれぞ 野をなつ可(か)し三(み) 一夜ね二(に)希(け)る」
課題はこの構成ですね。全てひらがなにすると以下のとおり。
はるののに すみれつみにと きたれしわれぞ のをなつかしみ ひとよねにける
漢字を入れると,
春の野に,すみれ摘みにと来し我ぞ,野をなつかしみ一夜寝にける
これは奈良時代の歌人「山部赤人」の歌となっております。
やまべのあかひと,と読みます。
「万葉集」の「巻八 1424」に収録されています。
「春の野に,すみれを摘もうと来た私だが,野の美しさに心惹かれて,一晩を過ごしてしまった」
…と言う風流な歌なのですが,
信州人、日中は暑く,夜は冷える感覚を持つ身としては,
「大丈夫?寒くない?凍えない?」と無粋に思ってしまいます。
奈良時代,奈良の文化圏を考えれば,スミレの時期はかなり暖かいのでしょうね。
温暖化前の時代であっても。ええ,そうだと思いますとも。
・
・
松本市美術館友の会のご縁で,ちょうど1年前,
御子柴さんの教え子の方と会う機会がありました。
友の会の総会で席に着くと,
私と御子柴さんの隣に小柄な女性の方がおひとり。
全くの偶然に,御子柴さんの教え子だと分かり,
お互いが再開を喜んでいる…これを目の当たりにし。

その1年後の今,
ご自身の飼われた,また飼っている猫をモチーフに,
絵を描き,塩尻市の「えんぱーく」3階で個展を開いている,と言うのです。
そこで知るのですが,「えんぱーく」は,
壁を展示用に貸し出しているのだそうで。
これを利用なさっているのだなぁ、と。
3月31日までの会期となっておりますので,
ご興味がある方は是非ともご覧になって下さい。
猫の絵しかなく猫の絵ばかりですが,
モチーフに有名な絵画などを使ったものもあり,
楽しむことができます。
保護猫の活動もされている方なので,
そうした意義ある活動の助けとなるよう,
この場でも少し宣伝させていただきます。
・
・
…と,そんなところでちょうどお時間となってございます。
冒頭は我が家のピーちゃんが愛嬌を振りまいて始まりました。
そんな楽しいひと時もここまでとなっております。
それではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年03月17日
「紅顔(腮)花欲綻」白居易詩より(競書誌「書象」2025年4月号,条幅課題より)

・
・
こんにちは,あるいはこんばんは。
信州塩尻市、欅の森書道会のウェブ担当,宗風です。
書道教室の研修日と研修日の間に挟まりまして,
本日は条幅の課題に使われております漢詩,
これにまつわる一席にて,
しばしのご愉快,お付き合いを願っておきます。
気楽なところがよろしいんじゃないか…と言うところですが,
一生懸命に申し上げることにしております。
どうぞ終いまで,気を確かに持って,共に頑張って行こうじゃありませんか。
いや,本当に,今回は気を張りそうな内容なんです。
教室の予定につきましては,前回のブログにも書きました通り,
変更の可能性がありはするけれど,
基本はこれで行こう…が,12月まで定まっております。
念のため,以下に再び貼付ます。
4月7日
4月21日
5月12日
5月26日
6月2日
6月23日
7月14日
7月28日
8月4日
8月18日
9月8日
9月22日
10月6日
10月20日
11月10日
11月17日
12月8日
12月22日
各月前半が競書の提出日となっております。
・
さて,競書の課題「紅顔花欲綻」が樋口玄山先生より届けられました。
行書での課題【漢字条幅】ですね。
漢詩の一部である訳ですが,この語句を含む漢詩,
その環境を本日のお題としてございます。
白居易,白楽天については,
過去何度も課題として,
また作品制作としても出会っておられるのではないかと思います。
白居易の「新楽府」には「鹽商婦」と言う詩があります。
「鹽」は「塩」の旧字ですね。
塩尻市に住む私達でも馴染みが…馴染みは無いですかね。
松本市の私の実家近くに「鹽竈神社」があるので,私個人としては馴染みがあるものですが。
これは数多くの作品を遺した白居易の時代の中でも,
若い頃の「諷諭詩」のひとつとなります。
師自身が自身の詩風を「諷諭」「閑適」「感傷」「雑律」としており,
最も重きを置いたもの,志を高く持ったものが「諷諭」に当たります。
「閑適」は「独善の義」を表現するもので,日本では理想の生活として受け入れられたのだそうです。
よって志と言うより生活の切り抜き,情景,喜び。
「諷諭」は「兼済の志」とし,才ある者が広くその知恵を広げ,救済に努めるべき詩情とし,
端的に言えば「こうしたら良いよ,なんで世の中はこうならないのか,そう思うだろう」の感覚、
だので,今回の「紅顔花欲綻」もまた社会を風刺した内容の一部なのです。
「諷諭」は,おそらくは環境の変化により,
次第に書かなくなった…書けなくなったもの,と考えます。風刺だからこそ。
ちなみに。
出展が「鹽商婦」と特定してしまっていますが,
この中に課題と全く同一の語句は存在していません。
「紅顔花欲綻」は「紅花腮欲綻」として掲載されています。
「腮」は「あご、えら」と読みます。
体の一部を表すニクヅキに思と言う構造。
故に、やはり頬なども連想させますよね。
耳下あたりの輪郭部も「えら」と言ったりします。
まずは例によって原文を。
白居易「新楽府」より,其三十八「鹽商婦」
鹽商婦 多金帛
不事田農與蠶績
南北東西不失家
風水爲郷船作宅
本是揚州小家女
嫁得西江大商客
綠鬟溜去金釵多
皓腕肥來銀釧窄
前呼蒼頭後叱婢
問爾因何得如此
婿作鹽商十五年
不属州縣属天子
毎年鹽利入官時
少入官家多入私
官家利薄私家厚
鹽鐵尚書遠不知
何況江頭魚米賤
紅膾黄櫨香稻飯
飽食濃妝倚柁樓
雨朵紅腮花欲綻
以上が原文となります。
続いて書き下し文を。
鹽商の婦,金帛多し
田農と蠶績とを事とせず
南北東西,家を失わず
風水を郷と為し,船を宅と作す
もとは是れ揚州小家の女
嫁ぎし得たり西江の大商客
綠鬟,溜り去って金釵,多く
皓腕,肥へ来って銀釧,窄(せま)し
前に蒼頭を呼び,後に婢を叱る
爾(=然る)に問ふ,何に因て此くの如きを得たる
婿は鹽商となって15年
州縣に属さず天子に属す
毎年鹽利の官に入る時
官家に入るは少く私に入るは多し
官家,利薄くして私家厚くも
鹽鐵尚書,遠くして知らず
何ぞ況んや江頭魚米賤しく
紅膾,黄櫨,香稻の飯,
飽食,濃妝,柁樓に倚り,
雨朵の紅腮花綻びんと欲するをや。
…と言ったような書き下し文になります。
課題の「紅顔花欲綻」は字面だけ見ると,
華やかで素敵な想像と共にやって来ますが,
この詩は風刺のひとつですから,
実は顔を紅潮させ花のほころびを待つ,
春の様相だけれど,安穏と構えて聞いて良いか…
…と言うと少し違うようで。
「鹽商婦」の意味,続けて行ってみましょう。
塩問屋の奥さん,金持ちである。
農耕も養蚕も何もしていないのに,
南北東西,どこにでも家を持ち,
風水を故郷として,船にも住むことができる。
元々は,揚州の普通の家の女だった。
嫁いだ先が,西江の大きな商家の家だった。
黒髪の髷(まげ)には,金の簪(かんざし)が多くあり,
肥え太った白い腕には銀の腕輪が窮屈そうに付いている。
前を向いては丁稚を呼び,後方では下働きの女を叱る。
しかに問う。どうやってそんなに(金を)得たのか知っているのか、と。
婿は塩問屋の婿は,婿になって15年になる。
地方役人ではなくて,中央直轄だ。
毎年,塩の利益を収める時に,
政府には少なめに,自分の家にたっぷりと。
政府の利が少なく,私腹を肥やしていたとしても,
塩や鉄を管轄する役所は遠く気付くことはない。
増して,川の近くに暮らしていれば,米や魚は安く,
赤い肉,黄ハゼ,香稲(香の高い米)と食らい,
(膾はなます,酢の料理でもあり細切りの肉とも言い。
この場合は豪勢な食事だろうから肉なのかなぁ)
飽食し,厚化粧をし,(船を家にしているので)操縦室にもたれかかり,
雨滴の向こう,両の頬がだらんと垂れ,花のように紅くなっている。
…と言う様な意味ではなかろうか,と思います。
色々と資料を読み漁って作成したので,
私見も入っているし正確ではないかも知れませんが。
塩で利をたっぷりと得て,
ある意味不正もしてお金はうなるほどあるのに,
施すようなこともせず,もう遊んでいると。
良い所に住んで、良いものを食べて…それで良いのか。
何と言うか,白居易が生きた時代は772年から846年と言われているので,
そんな時代からも人の世ですから腐敗はあるよね…
…なんて思わずにはいられませんね。
今のテレビも多く,そうした部分が多いですものね。
いや、政治の話をしたいのではないのです。
大切なことではあるけれど、
趣味の、だからこそ楽しい書道教室だと思いますので、
そちらの話はそちらの方でが正しいかしら。
ともあれ、実は今回の課題の背景には、そんな白居易の思い…
…想いと言うか、風刺があるのだと、
長講一席,解説させていただきまして、
ちょうどお時間となっているようでございます。
それではまた来週の教室でお会いできる方はお会いいたしましょう。
宗風でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年03月11日
3月10日は欅の森書道会の研修日でした+2025年後半の教室の予定について。

・
・
こんにちは、あるいはこんばんは。
信州塩尻市、欅の森書道会のウェブ担当、
お馴染み宗風でございます。少し間が空いての登場となります。
無沙汰を申し訳なく思っております。
何はともあれ、本日も気楽なところで一生懸命…と言うことですが。
本来は「三寒四温」と言う言葉は、
暖かいと寒いを繰り返して春を向かうような…
聞くと「七寒」の冬に比べて、ちょっと気分が上がる言葉かな、と、
個人的には思ったりもいたします。
今年はどうなんでしょう。緩やかに変わって来るというよりも、
ドンと寒く、ドンと暑く、1日のうちの温度差も激しく、
厳しい気候のことを「試される大地」なんと申したりする世の中ですけれど、
どこかそんな気配が感じられる…そう思うのです。
ともあれ、3月10日の欅の森書道会では、
月例、競書作品の提出日でありながら、
目下、書象展への作品制作が盛んに行われており、賑わっておりましたね。
皆さん、進捗はいかがでしょうか。
次回の3月24日が〆切となっておりますので,
どうか、お互いに励んで行こうではありませんか。
意気また努力が実りますように,祈っております。
・
また来年のことを言うと鬼が笑うなんてことを、よく申しますよね。
来年のことは申し上げませんけれども、
来年の直前までのお話があります。
2025年12月までの教室の予定が決まりました。
これは以下のとおりです。
4月7日
4月21日
5月12日
5月26日
6月2日
6月23日
7月14日
7月28日
(7月13日の日曜日は県展の添削会とのこと)
8月4日
8月18日
9月8日
9月22日
10月6日
10月20日
11月10日
11月17日
12月8日
12月22日
ついでに申し上げますと、
松本市美術館友の会の書道ワークショップが、
7月21日だったりします。今年で3年目です。
御子柴さんと共に、頑張ってやって来ますね。
こう、昨晩の後半にて、
池口さん、二木さんとお揃いのタイミングで、
玄山先生と共にスケジュールが決まっていきましたが、
「ああ、もう年末の話も出るのだなぁ」とは、思うものでした。
あっと言う間に過ぎて行くのですけれど、
でも「遠い話だなぁ」とは感じました。
それまで皆さん、元気に元気に元気に!頑張って行きましょう。
ちなみに。
現状の予定は一部で流動的となる場合がある、とのことです。
現に11月も連休を避ける場合に、続けての開催となっていたりします。
玄山先生が競書の審査を行われるそうで、
その対応との兼ね合いが出て来る…とのことでした。
変更などは連絡網なども含めてもお伝えして行きますので、
まずは年末までの予定を決めたよ…とご承知おき下さい。
先生から条幅のお手本は頂戴しておりますが、
まだ言葉を調べ切れておりませんので、
本日は予定のお知らせまでとなります。
来週までには言葉の解説でも1本,ブログにできると良いのですが。
三寒四温だけでなく、気圧も乱高下をしており、
気持ちも浮き沈みが激しいことこそ春の訪れのようにも感じます。
15日前後に競書誌「書象」の4月号も届くはず。
それでは皆様また次回にお目見えいたします。
お読みいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
・
・